節税方法って何があるの?お金のプロが動画で詳しく解説!
年収1000万円台の方は必見!節税の仕組み・選択肢・年収別の節税効果をわかりやすく解説します。
不動産投資のみならず、生命保険控除、確定拠出年金、ふるさと納税などそれぞれの特徴を約25分間に凝縮しておりますので、税金対策を実践したい方はぜひ参考にしてください。
どなたでも無料でダウンロードいただけます。
※お申込みいただいた動画セミナーもご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。
Amazonギフトカード
プレゼント条件
【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。
プレゼント条件
プレゼント対象外
【ご⾯談についての注意事項】
【その他注意事項】
当社の取り扱い商品の特徴
ご注意

年収1,000万円を超えたサラリーマンは、所得税と住民税の合計税率が30%を超え、社会保険料も上昇してしまうため、思っている以上に手取りは少なくなってしまいます。1000万円は会社員が憧れる一つの目標にしている人も多いですが、税金などの負担が重いために達成してもあまりお金が増えた気がしないと、実際に達成した人の多くが感じています。
少しでも手取りを多くして、豊かな生活を実現するためには、税金対策が必須です。
年収1000万円クラスになると、効果的な税金対策はさまざまな方法があるものの、その中でも特に節税効果が大きくお勧めなのは、不動産投資です。
本記事では、年収1,000万円を超えたサラリーマンが税金対策をするべき理由、新NISAをはじめとした節税方法について説明します。特におすすめしたい不動産投資は手厚く解説していくので、効果的な税金対策を行っていきたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
節税方法って何があるの?お金のプロが動画で詳しく解説!
年収1000万円台の方は必見!節税の仕組み・選択肢・年収別の節税効果をわかりやすく解説します。
不動産投資のみならず、生命保険控除、確定拠出年金、ふるさと納税などそれぞれの特徴を約25分間に凝縮しておりますので、税金対策を実践したい方はぜひ参考にしてください。
どなたでも無料でダウンロードいただけます。
※お申込みいただいた動画セミナーもご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。
目次
 年収1,000万円を超えたサラリーマンが税金対策をするべき理由は、次のとおりです。
年収1,000万円を超えたサラリーマンが税金対策をするべき理由は、次のとおりです。
・所得税と住民税の合計税率が30%になるから
・社会保険料は年収とともに上がるから
・収入が増えると生活レベルが上がり、手元にお金が残りにくくなるから
年収1,000万円を超えてくると、税金・社会保険料ともにかなり高額になります。節税方法を理解する前に、まずはなぜ年収1,000万円を超えたサラリーマンが税金対策しなければならないのか見ていきましょう。
年収1,000万円になると所得税と住民税の合計税率が30%となり、相当な税額を負担しなければなりません。年収1,000万円の課税所得金額は家族構成等によって異なるものの、おおよそ670万円といわれています。
課税所得金額が670万円の場合には次の表のとおり、所得税率20%が適用されます。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
| 1,000円以上 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)
また、所得税と別に住民税が課税されます。住民税の税率は自治体によって異なるものの、多くの自治体では税率10%プラス5,000円を課しています。
つまり、年収1,000万円のサラリーマンには、所得税と住民税で約30%の税率が課されるということです。
年収1,000万円・課税所得金額670万円の場合、所得税・住民税がいくら課税されるのか計算してみましょう。
| 【所得税】 6,700,000円 × 20% – 427,500円 = 912,500円【住民税】 6,700,000円 × 10% + 5,000円 = 675,000円 |
シミュレーションでは、所得税と住民税の合計納税額は1,587,500円となります。実際には社会保険料もかかってくるので、手取りは想像以上に少なくなってしまいます。この多額の納税額を取り戻すためには個別の節税対策が必須です。
社会保険料は年収が多くなるほど高くなり、年収1,230万円まで上昇していきます。年収1,000万円のサラリーマンは厚生年金だけで約91万円払わなければなりません。
社会保険料は所得控除の対象となるものの、約91万円というのは大きい負担です。
所得税や住民税、社会保険料の支払額を考えると、年収1,000万円のサラリーマンの手残り金額は決して多いとはいえないと、理解できるのではないでしょうか。年収1000万円になっても、あまり増えた感じがしないというのは、この負担の大きさからきています。
収入が増えると、生活水準も自然と上がっていきます。例えば、広い家に引っ越したり、高級な車を購入したり、豪華な旅行に出かけたりがその一例です。これは「ライフスタイル・インフレーション」と呼ばれる現象で、多くの人が経験します。
年収が500万円から1000万円に倍増したとしても、生活費が2倍になれば、手元に残るお金はあまり変わらなくなってしまうでしょう。むしろ、高所得者向けの商品やサービスは割高な場合もあり、収入以上に支出が増えてしまうケースもあります。
この状況を改善するには、収入が増えても生活水準に比例して支出を上げないように注意が必要です。さらに大切なのは、節税対策を積極的に行い、手取り額を増やすのが重要になります。不動産投資や確定拠出年金、ふるさと納税など、さまざまな方法を検討し、自分に合う節税対策を実践しましょう。
 年収1,000万円を超えたサラリーマンの税金・社会保険料は高額になるものの、効果的に金額を抑える方法があります。年収1,000万円を超えたサラリーマンに有効的な税金対策は、次のとおりです。
年収1,000万円を超えたサラリーマンの税金・社会保険料は高額になるものの、効果的に金額を抑える方法があります。年収1,000万円を超えたサラリーマンに有効的な税金対策は、次のとおりです。
・新NISA
・iDeCo(イデコ)
・ふるさと納税
・配偶者控除や扶養控除
・生命保険料控除や地震保険料控除
・医療費控除
・住宅ローン控除
・不動産投資
各種項目がなぜ税金対策になるのか、実際にどの程度税金が減るのかシミュレーションしていきます。人によって利用できる項目とできない項目があるため、内容を確認して自分がどの方法で税金対策するのかの判断材料にしてみてください。
所得税を減らすには、節税の知識が必須です。J.P. Returnsでは、節税対策の方法をわかりやすく解説しているeBookを公開しています。フォームに入力するだけで、無料で資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。
30秒で完了
新NISAは2024年から開始され、非課税枠内の株式投資や投資信託の譲渡益・運用益が非課税になる制度です。国内株だけでなく、米国株も範囲となっており、多くの投資家が活用しています。
通常、株式投資や投資信託の利益に対しては、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。所得税・住民税・復興特別所得税の合計税率は20.315%です。株式投資や投資信託の運用益に対しては分離課税で計算され、給与所得や事業所得などの他の所得とは別に税額を計算します。
株式投資などで年間100万円の利益が出た場合、次のような税額が課されます。
| 【所得税】100万円 × 15% = 15万円
【住民税】100万円 × 5% = 5万円 【復興特別所得税】100万円 × 0.315% = 3,150円 【合計】 20万3,150円 |
新NISAは非課税枠内の譲渡益・運用益に課税されないため、年間100万円の所得があっても約20万円の納税は必要ありません。さらに今回の改正で非課税期間の制限が撤廃されました。そのため、数十年以上の運用に当たっても税金がかかりません。長く運用すると数百万円以上、投資金額が大きい人は1000万円近くの税金を節税できるでしょう。
iDeCo(イデコ)とは私的年金制度です。
iDeCoは自分で投資商品を選択し、掛金を支払っていきます。投資して得た運用益には税金が課税されず、掛金については全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
iDeCoを利用した場合、いくら節税できるのか見ていきましょう。
| 【シミュレーション条件】 ・年収1,000万円、30歳サラリーマン ・毎月の掛金2万円 ・運用利回り2.0% ・60歳で受給 ・企業型確定拠出年金(企業型DC)・確定給付企業年金(DB)ともに加入していない |
上記の内容では、以下のような節税効果があります。
| 【拠出時】 ・毎月の節税効果:7万3,000円 ・30年間の節税効果:217万4,000円【運用時】 ・52万6,425円(30年運用の場合) |
※ろうきんのiDeCoシミュレーターを利用し計算
iDeCoを活用した節税についてより詳しく解説した記事もあります。ぜひ合わせて確認してみてください。
> iDeCoで節税できる仕組みは?節税額やメリットを解説
ふるさと納税とは、特定の自治体に寄付できる制度で、厳密には節税対策ではありません。しかし、自己負担額2000円で、寄付額に応じた各地の返礼品を受け取れるので、高所得者にとっては魅力的な選択肢となります。
年収1000万円にもなると、寄付できる限度額も大きくなるため、2000円(自己負担額)以上の魅力的な特産品を受け取れるでしょう。
寄付する自治体が5つ以内であれば、ワンストップ特例を利用して、簡単に手続きができ、寄付金控除分の金額が住民税から減額されます。ただし、減額される寄付金控除には上限があり、上限を超えた分は減税されなくなるため注意しましょう。
なお、寄付金控除の上限は年収や世帯によって異なります。どの程度控除が受けられるのかは、総務省の「寄附金控除額の計算シミュレーション」をダウンロードするなどしてご確認ください。
配偶者控除や扶養控除を利用すれば、税金が減額されます。
配偶者控除は納税者の所得が1,000万円以下の場合、次の表の控除が受けられます。年収1,000万円の場合は課税所得金額が670万円程度になるため、一般の控除対象配偶者であれば38万円が控除額です。
| 控除を受ける納税者本人の
合計所得金額 |
控除額 | |
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」)
また、配偶者の年間の合計所得金額が、48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であるのも、配偶者控除を利用できる条件になります。
扶養控除を受けられるかどうかは、本人の所得は関係なく、扶養される人に条件があるだけです。扶養される人の年間合計所得金額が、48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であるなどが適用される条件になります。
| 区分 | 控除額 | |
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
(出典:国税庁「No.1180 扶養控除」)
生命保険料や地震保険料を支払っている場合、払込金額に応じて生命保険料控除や地震保険料控除が受けられます。
生命保険料控除は、新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料それぞれ個別に計算します。
計算方法は、次の表のとおりです。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約に適用される計算式
(出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」)
新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料それぞれの控除額上限は4万円であり、合計した控除額上限は12万円です。
地震保険料控除の計算方法は、次の表のとおりです。地震保険料控除の所得税は最大5万円、住民税は最大2万5,000円が課税所得金額から控除できます。
| 区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
| (1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 | |
| (2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 10,000円超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
| 20,000円超 | 15,000円 | |
| (1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
(出典:国税庁「No.1145 地震保険料控除」)
医療費控除は、医療費に使った年間の支払額に応じて控除を受けられる税制です。
医療費控除が受けられるのは納税者本人と、生計を一にする親族の支払った医療費合計額が10万円を超えた場合です。
医療費控除の最大控除額は200万円であり、下記の計算式で控除額を計算します。
| (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約で支給される入院費給付金や健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2)10万円 |
(出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」)
なお、医療費控除を利用する場合、確定申告にて申告する必要があります。年末調整では、医療費控除が使えない点には注意しましょう。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じた金額が所得税から控除される税制です。2024年・2025年中に住宅ローンで購入した住宅に入居する場合、次の表の内容が適用されます。
| 住宅新旧等 | 住宅環境性能等 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除割合 |
| 令和6・7年入居 | ||||
| 新築住宅
買取再販 |
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 |
4,500万円 | 13年間 | 0.7% |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年間 | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 13年間 | ||
| その他住宅 | 0円(※) | – | ||
| 既存住宅 | 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 10年間 | |
| その他住宅 | 2,000万円 | 10年間 |
※一般の新築住宅のうち令和5年12月31日までに建築確認を受けたものか、令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。
(出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」)
住宅ローン控除で、どの程度の所得控除が受けられるのか計算してみましょう。
| 【シミュレーション条件】 ● 新築の認定長期優良住宅を購入 ● 13年間、年末の借入残高は4,500万円以上あると仮定(借入限度額4,500万円)【シミュレーション計算】 4,500万円 × 0.7 × 13年 = 409万5,000円 |
上記の計算例の場合は、13年合計で約409万円もの所得税が減税されます。住宅ローン控除の控除額よりも所得税の方が低い場合、残額を住民税から控除します。ただし、住民税から控除できるのは最大9万7,500円までです。
不動産投資は、年収1000万円クラスの高所得者にとって非常に効果的な節税対策です。不動産所得の赤字を給与所得と合算して、課税所得を圧縮できるために収める税金を減らせる仕組みです。
特に年収1000万円以上の方々は、高い税率が適用されるため、不動産投資による節税効果が顕著に表れます。所得税と住民税だけでも約30%の税率が課されるため、課税所得の圧縮による節税効果は大きくなります。
さらに、不動産投資の魅力は節税だけにとどまりません。適切な物件を選択すれば、家賃収入という形で安定的なキャッシュフローを得られます。また、中長期的に価値を保たれる物件であれば、効率的な資産形成にも寄与するでしょう。
高所得者の税負担を軽減しつつ、将来の資産形成にもなるのが不動産投資の魅力です。資産形成での観点では、次の章以降で詳しく説明していきます。
 年収1,000万円を超えたサラリーマンには、多くの税金対策がありますが、その中で最もおすすめなのは不動産投資です。なぜなら、税金対策以外のさまざまなメリットが享受できるからです。不動産投資が特におすすめできる以下5つの理由を説明していきます。
年収1,000万円を超えたサラリーマンには、多くの税金対策がありますが、その中で最もおすすめなのは不動産投資です。なぜなら、税金対策以外のさまざまなメリットが享受できるからです。不動産投資が特におすすめできる以下5つの理由を説明していきます。
・節税しながら資産形成にもなる
・赤字が発生しても損益通算で所得を減らせる
・実務の多くを管理会社に委託できる
・インフレ対策になる
・レバレッジ効果がある
それぞれ詳しく解説していきます。
不動産投資は、節税をして手元の資金を増やしつつ、同時に資産形成にもなります。特に年収1000万円クラスの高所得者は、高い税率が適用されるため、課税所得の圧縮による節税は高い効果が見込めます。
同時に、不動産投資は長期的な資産形成にも貢献するでしょう。優良物件を購入すれば、安定した家賃収入が得られるだけでなく、中長期的には不動産価値の上昇も期待でき、効果的な資産形成となります。
ローン返済は、主に家賃収入を返済の原資とできるため、自己資金からの持ち出しを最小限に抑えながら、資産を形成できるのも大きなメリットです。このように、不動産投資は節税対策、資産形成の両方の面からも望ましい戦略といえるでしょう。
不動産投資では、思った以上に集客に苦労するなど、想定以上に空室が長引いてしまう可能性もあるでしょう。しかし、不動産投資で赤字が出ても給与所得と損益通算で、課税所得を圧縮できるため、赤字のダメージを最小限に抑えられます。
不動産投資における損益通算とは、不動産投資で発生した赤字を、給与所得や事業所得などから赤字を差し引いて所得を圧縮できる税制です。
例えば、給与所得700万円のサラリーマンが、不動産投資で200万円の赤字を出したとします。このような場合、給与所得を500万円に抑えることが可能です。給与所得700万円のままだと所得税率23%が適用されますが、500万に抑えられれば税率が20%に下がります。
減価償却費の計上によって、実際の赤字額よりも会計上は大きな赤字にできるため、節税効果も高くなります。自分の年収でどれくらい節税になるかを詳しく知りたい場合は、プロのコンサルタントへの無料相談を活用してみてください。
さらに詳しく知りたい人は、不動産投資の赤字で節税できる理由についてより解説した記事もあるので、併せて確認してみてください。
> 不動産投資の赤字で節税できる理由|良い赤字・悪い赤字の違いも解説
年収1000万円クラスの人の多くは、「仕事が忙しいので、不動産投資をやる時間がないと」考えるかもしれません。しかし、不動産投資は、実務の多くを管理会社に委託できます。
不動産投資は不動産の管理が手間と考えている方も多くいますが、次のような業務は管理会社に任せられます。
| 入居者管理 | ● 入居者募集 ● 賃貸契約関連手続き ● 家賃の入金確認 ● 滞納者への対応 ● トラブル対応 ● クレーム対応 |
| 建物管理 | ● 建物と設備の維持管理 ● 清掃業務 ● 長期修繕計画の策定と実施 |
上記の表のように、不動産投資で必要なほとんどの実務を管理会社が代行してくれます。投資家は不動産の購入や売却、投資計画の策定などだけを行えばよいだけなので、手間はかかりません。税理士などに確定申告の依頼もすれば、ほとんど不動産オーナーの手間をかけずに節税が可能になります。
不動産投資はインフレ対策として、保有している資産の価値保全にもなります。
インフレが起こると一般的に不動産の価値は上がる傾向にあり、一方、現金の価値は相対的に目減りしていきます。また、インフレによって家賃収入の上昇が期待できるのもメリットです。
現金の価値が下がれば、ローン残額の負担感も減っていきます。さらに、返済金額は一定でも、家賃の金額が上がれば返済が楽になるでしょう。
ただし、不動産投資用ローンの金利が上昇し、返済額が増える可能性もある点には注意が必要です。変動金利で設定されている金利は、インフレの影響を受けやすいからです。金利上昇による返済金額の増額によって、経営が厳しくなると予想されるなら、固定金利を採用するのも一つの選択肢となります。
不動産投資の方法も含めたインフレ対策を紹介した記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
> 個人でできる具体的なインフレ対策を紹介|不動産投資がおすすめできる5つの理由
不動産投資では、レバレッジ効果があるので、少ない資金で効率的に資産を増やせます。
不動産投資におけるレバレッジとは、融資を受けて自己資金では購入できない不動産を手に入れることです。株式投資では基本的に保有している資金分しか運用に回せませんが、不動産投資は自己資金だけでは購入できない大きな投資ができます。
例えば、不動産投資では自己資金1,000万円で家賃収入が年間100万円なら利回り10%です。一方、不動産投資ローン2,000万円を合わせた合計3,000万円で利回り10%だと、年間300万円となり収入額に大きな差が生まれます。もちろん、ローン返済があるので、手元に残るお金がここまでの違いになるわけではないですが、ローン返済後に保有している不動産の価値には大きな差が生まれるでしょう。仮にそれぞれ物件の価値が1割落ちたとしても、前者は900万円で後者は2700万円となり、保有資産は雲泥の差になります。
レバレッジ効果で自己資金以上の金額を運用できて、大きな資産を築きやすいという点も不動産投資の大きなメリットです。
不動産投資のレバレッジ効果についてより詳しく解説した記事もあるので、合わせて確認してみてください。
> 不動産投資のレバレッジ効果を解説!利回りの目安やリスクもチェック
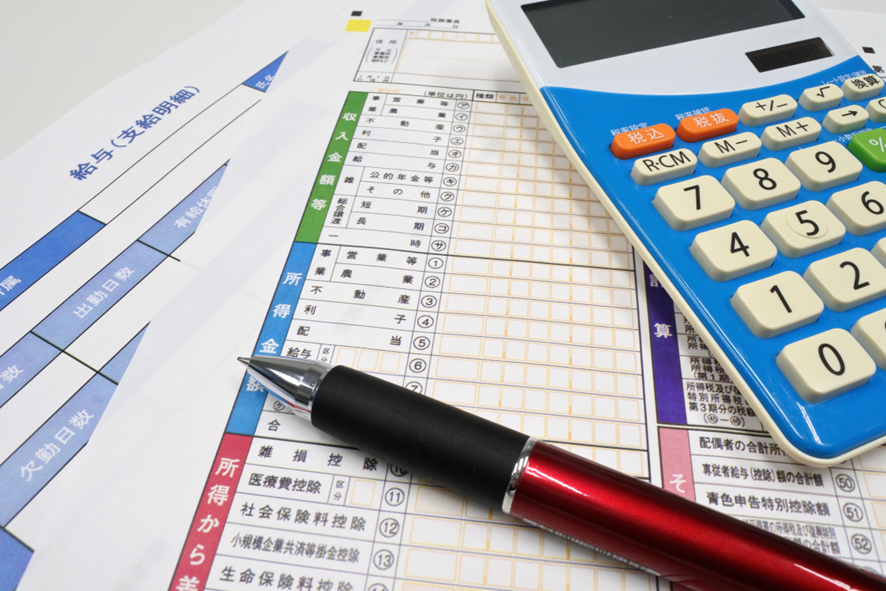 不動産投資は先述の通り、高い節税効果を持ちながら、資産運用面でも有利となる資産運用方法ですが、ポイントを押さえて始めないとかえって資産を減らしてしまう可能性もあります。致命的な失敗を避けるためにも、以下の点を注意してください。
不動産投資は先述の通り、高い節税効果を持ちながら、資産運用面でも有利となる資産運用方法ですが、ポイントを押さえて始めないとかえって資産を減らしてしまう可能性もあります。致命的な失敗を避けるためにも、以下の点を注意してください。
・詐欺に気を付ける
・物件選びで手を抜かない
・さまざまなリスクもある
・短期で大きな利益は出せない
・節税のみを目的として不動産投資を始めない
それぞれ詳しく解説していきます。
不動産投資は、残念ながらさまざまな詐欺が横行しており、巻き込まれてしまうと借金だけ残ってしまうケースもあるため、注意してください。
代表的な詐欺として、実際には存在しない物件や、他の人が所有権を持っている物件を偽装して販売する架空物件詐欺があります。投資家は多額の資金を失うだけでなく、法的トラブルに巻き込まれる可能性もあるでしょう。
また、収益を実際よりも高く見せる行為もよく耳にします。この手口では、物件の収益性を過大に表示し、騙して買わせようとします。例えば、家賃相場よりも高い家賃収入を約束したり、空室率を低く見積もったりといった行為です。購入してしまうと、赤字続きで苦労してしまいます。
このような詐欺に遭うと、金銭的損失はもちろん、精神的苦痛も大きいです。最悪の場合、借入金の返済が滞り、個人の信用が大きく損なわれる恐れもあります。物件を手放すにも大きく値下がりしていて、借金だけ残るケースもあります。信頼できる不動産会社から購入すれば、詐欺に遭う可能性を限りなくゼロに近づけられるでしょう。おいしすぎる話は何か理由があると、常に警戒心を持っておくことが騙されないためには大切です。
物件選びは不動産投資の成功を左右する最も重要な要素といっても過言ではありません。立地、建物の状態、エリアの将来性、価格などを総合的に見て、全力で物件選びに取り組みましょう。
適切な物件を選べると、安定した賃料収入や将来の資産価値上昇が期待でき、安心して長期的に運用ができます。一方、不適切な物件を選んでしまうと、空室率の上昇、賃料の下落、予期せぬ修繕費用など、さまざまな問題に直面してしまいます。
いったん購入してしまえば、物件そのものの特性を改善するのは非常に困難です。例えば、立地の悪さは、どんなに内装を改善しても解決できません。また、建物の構造的な問題は、多額の費用をかけても完全には解消できない場合があります。
つまり、物件選びで失敗すると、その後どれだけ努力しても、投資成果の大きな改善は望みにくいです。逆にいえば、適切な物件を選べれば、その後の不動産オーナーの仕事はほとんどなく、投資の成功に向けて大きく前進できます。
物件選びに自信がない方には、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。J.P.RETURNSでは無料個別相談を提供しており、経験豊富な専門家が、あなたの投資目的や予算に合わせた物件選びをサポートします。この機会を活用して、資産形成の確実な第一歩を踏み出してみてください。
不動産投資には、慎重な物件選びを行っても完全にリスクをゼロにはできません。しかし、事前にリスク対策や備えをしておけば、不動産投資を辞めざるを得ないような致命的な状態に陥る事態を避けられます。
いくつか代表的なリスクを紹介します。不動産の価値が下がる物件価格下落リスク、収入が減ってしまう家賃下落リスク、ローン返済負担が大きくなる金利上昇リスク、建物に損害を負う危険のある災害リスクなどです。
しかし、これらのリスクは適切な対策により軽減可能です。例えば、資産価値が落ちにくい需要の高い人気エリアの物件を選ぶ、複数の物件に分散投資するなどが挙げられます。
さらに、現金に余裕を持っておくと、突発的な出費や想定以上の空室が続く際も安心して対応ができます。
このようなリスク対策や備えをしておくと、不測の事態に直面しても、安心して対応できるでしょう。
不動産投資は、短期間で大きな利益を得る手段としては適していません。なぜなら、不動産は流動性が低く、取引コストも高いため、短期間での売買で大きな利益を出す投資モデルではないからです。
例えば、物件購入時には、不動産取得税、登記費用、仲介手数料など、物件価格の5%~10%程度の初期費用がかかるので、これらの費用を回収するだけでもそれなりの時間を要します。また、不動産価格の変動は通常緩やかであり、短期間で大幅な値上がりをするのは、再開発地域になったなど、大きな外部要因がある場合のみで、一般の人が予測するのは現実的ではありません。
一方で、長期的な視点で不動産投資に取り組めば、再現性高く大きな利益を得られるでしょう。中長期でのシミュレーションを綿密に行い、市場の短期的な変動に左右されず、粘り強く運用を続けるのが成功への鍵となります。
不動産投資を単なる節税手段として捉えるのは危険です。確かに、適切な物件を選んで行えば節税効果は得られますが、これを主目的にすると大きな落とし穴に陥る可能性があります。節税目的だからといって、適当に物件を購入すると、節税額を大幅に上回る赤字を抱え、結果的に手元資金を減らしてしまうでしょう。
例えば、需要の低い物件を購入すれば、空室率の上昇や賃料の下落により、想定以上の損失が発生し、節税効果以上のマイナスになってしまいます。
不動産投資を事業と捉え、安定した収益の獲得を目的として始められれば、失敗する確率を大幅に減らせます。節税はあくまで副次的な効果と捉え、資産運用の商品としての質や将来性を重視した投資判断を行うべきです。
 年収1000万円の方々にとって、不動産投資は節税面も資産運用面でも非常に魅力的な選択肢です。適切な方法で行えば、効果的な節税対策となるだけでなく、長期的な資産形成にも大きく貢献し、経済的な不安を限りなく低くできるでしょう。ただし、本記事で解説したように、さまざまなメリットがあると同時にリスクの存在も忘れてはいけません。
年収1000万円の方々にとって、不動産投資は節税面も資産運用面でも非常に魅力的な選択肢です。適切な方法で行えば、効果的な節税対策となるだけでなく、長期的な資産形成にも大きく貢献し、経済的な不安を限りなく低くできるでしょう。ただし、本記事で解説したように、さまざまなメリットがあると同時にリスクの存在も忘れてはいけません。
単なる節税目的ではなく、不動産経営として円滑に運営できるかの視点を持つのが重要です。中長期的な収益性を意識して物件を選べば、失敗する確率を大きく減らせます。
不動産投資をすれば、自分の年収で具体的にどれくらい節税になるかを知りたい、あるいは物件選びを一人でやるのに不安を感じる方は、J.P.RETURNSの無料個人面談をご活用ください。一人一人の運用目的に合わせて、適切な物件を紹介致します。
節税方法って何があるの?お金のプロが動画で詳しく解説!
年収1000万円台の方は必見!節税の仕組み・選択肢・年収別の節税効果をわかりやすく解説します。
不動産投資のみならず、生命保険控除、確定拠出年金、ふるさと納税などそれぞれの特徴を約25分間に凝縮しておりますので、税金対策を実践したい方はぜひ参考にしてください。
どなたでも無料でダウンロードいただけます。
※お申込みいただいた動画セミナーもご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長
J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。
【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0
【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。
【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)